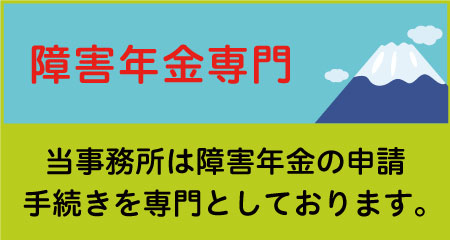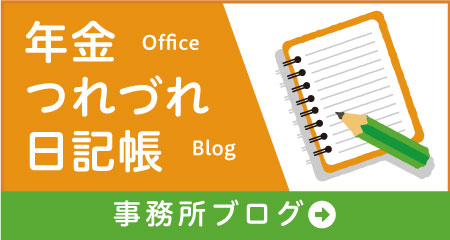障害年金の申請手順を解説
~初めての人は何から始めればいい?~
障害や病気で生活や仕事に制限が出てしまったとき、経済的な支えになるのが「障害年金」です。しかし実際に申請しようとすると「どこに行けばいいの?」「何から始めるの?」と戸惑う方が多いのも事実です。ここでは、初めての方でもわかりやすいように、申請の流れをステップごとに紹介します。
ステップ1:初診日を確認する
障害年金の申請で最も大切なのが「初診日」です。これは、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日を指します。年金制度では、この初診日にどの年金制度に加入していたかによって「障害基礎年金」か「障害厚生年金」かが決まります。まずは当時通っていた病院を思い出し、カルテや受診記録を確認しましょう。もし病院が閉院している場合は、当時の紹介状等や2番目以降の医療機関で作成された受信状況等証明書から証明できることもあります。
ステップ2:年金加入状況を確認する
障害年金は、保険料の納付要件を満たしていることが必要です。具体的には「初診日の前日に、一定期間以上保険料を納めていること」が条件となります。ねんきんネットや年金事務所で記録を確認してみましょう。(例外として、20歳前障害は保険料納付要件はとわれません。)
ステップ3:診断書を医師に依頼する
次に必要なのが医師の「診断書」です。障害年金専用の様式があり、身体障害、精神障害など障害の種類によってフォーマットが異なります。自分で用紙を用意して主治医に作成を依頼します。診断書の内容は審査の大きな判断材料になるため、症状や日常生活への影響をしっかり書いてもらうことが重要です。
ステップ4:申立書やその他の書類を準備する
「病歴・就労状況等申立書」と呼ばれる書類では、これまでの病気の経過や生活の状況を自分の言葉で記載します。少し面倒に感じますが、ここで自分の困りごとを具体的に伝えることが大切です。(論点がずれた書き方に注意)加えて、戸籍謄本や銀行通帳のコピーなどの添付書類も必要になります。
ステップ5:年金事務所に提出
書類が揃ったら、年金事務所に提出します。不備があると差し戻されることもあるので、窓口でチェックしてもらいながら進めると安心です。
ステップ6:審査と結果通知
提出後は日本年金機構で審査が行われ、数か月後に結果が通知されます。支給が決まれば、指定口座に年金が振り込まれる流れです。もし不支給となった場合は不服申立てを行う制度がありますが、不支給決定を覆すのは容易なことではありません。そのため初回の申請が大切です。
まとめ
障害年金の申請は、一見複雑に感じますが「初診日を確認 → 年金加入状況を確認 → 診断書を依頼 → 書類を揃えて提出」という流れを押さえれば整理できます。わからないことがあれば、年金事務所等に相談するのもおすすめです。一人で抱え込まず、サポートを得ながら進めていきましょう。